- BROOK’S OFFICIAL BLOGトップ >
- お楽しみ、コーヒーに似合うスイーツ
- > ふたつの「水無月(みなづき)」
ふたつの「水無月(みなづき)」

 6月のこの時季を現代では「梅雨」と呼びますが、陰暦(旧暦)では「水無月(みなづき)」と呼んでいました。雨が多い月なのに、なぜ水が無いと表すのでしょう?
6月のこの時季を現代では「梅雨」と呼びますが、陰暦(旧暦)では「水無月(みなづき)」と呼んでいました。雨が多い月なのに、なぜ水が無いと表すのでしょう?
今回は陰暦の「水無月」と、同じ名前をもつ和菓子の「水無月」、ふたつの「水無月」についてご紹介します。
■「水無月=水が無い」という意味ではなかった
十二ヶ月をそれぞれの季節に合った、呼称で表現する和風月名。「水無月」という呼び名の由来にも諸説あるようですが、有力視されているのが『田に水を引く(入れる)水の月=水無月』というもの。
この場合「無」は「無い」ではなく、連体助詞「な」という意味で、現代語に置換えると「の」にあたるそう。それで、“水無月=水な月=水の月”という意味で使われていたのですね。これなら現代の季節とも合っていて、わたし達にもしっくりきます。
■もうひとつの「水無月」
以前、おはぎとぼたもちの記事でもご紹介しましたが、日本では古くから季節や暦と和菓子が密接な関係をもっています。6月の旬の食材である稚鮎をかたどった「和あゆ」という菓子や、季節の花である紫陽花を模したねりきりなどがあり、代表格と言えるのが6月の陰暦「水無月」と同じ名前の和菓子「水無月」です。
■「水無月」ってどんな和菓子?
 羊羹に似た外郎(ういろう)生地に、小豆をのせた「水無月」。和菓子の本場、京都をはじめ関西で特に親しまれていて、京都人の中には「これを食べずに6月は越せない」という人もめずらしくないとか。
羊羹に似た外郎(ういろう)生地に、小豆をのせた「水無月」。和菓子の本場、京都をはじめ関西で特に親しまれていて、京都人の中には「これを食べずに6月は越せない」という人もめずらしくないとか。
和菓子「水無月」の由来は、旧暦の6月1日が「氷の節句」とされていたようで、その日に暑気払いとして氷室から氷を切り出して食べた、宮中の風習からきているそうです。しかし、現代と違って当時の氷は貴重品。宮中の人々以外は、暑い夏に氷を口にしたくても難しかったのでしょう。そのため庶民は小麦粉を練って三角形にし、氷片に見立てて食べたそうです。特徴的な三角の形は、氷を表していたのですね。
■1年の折り返しに“穢(けが)れ”を祓う「夏越祓(なごしのはらえ)」
 6月に「水無月」を食べる理由にも、古くからの行事が関係していました。1年のしめくくりに厄災を祓う大晦日(大祓:おおはらえ)に対し、1年の折り返しである6月末に半年分の罪や穢れを祓い、残り半年の無病息災を祈願する祭祀「夏越祓」。その際に食べられてきたのが、暑気払い・厄払いに見立てた和菓子「水無月」なのです。
6月に「水無月」を食べる理由にも、古くからの行事が関係していました。1年のしめくくりに厄災を祓う大晦日(大祓:おおはらえ)に対し、1年の折り返しである6月末に半年分の罪や穢れを祓い、残り半年の無病息災を祈願する祭祀「夏越祓」。その際に食べられてきたのが、暑気払い・厄払いに見立てた和菓子「水無月」なのです。
「夏越祓」では「水無月」食べるだけではなく、神社で茅(ちがや)という草で編んだ輪をくぐって穢れを落とす「茅の輪くぐり」や、人の形を模した紙の人形(ひとがた)を身代わりとして厄を落とすなどの行事を行うそうです。
来週の金曜日は6月30日、「夏越祓」の日です。
湿度が高くすっきりしない天気が続くこの時季、冷えたコーヒーや日本茶と「水無月」で暑気を払いできる現代人は、恵まれていますね!
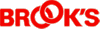





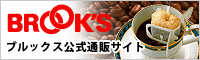


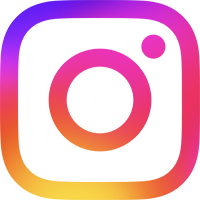

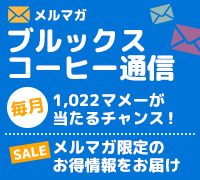
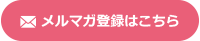




何気なく読ませて戴いたお陰様でスッキリいたしました。奥深い、風流の分かる国の子孫に生まれて良かった。自分も日本人の心意気を大事にしていきたいと思います。
Posted at 2017.06.28 by conoha
陰暦の「水無月」と、和菓子の「水無月」
ちょっと自慢したくなりました( *´艸`)イヒヒ♪
Posted at 2017.06.23 by パンサー