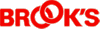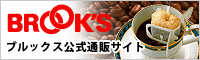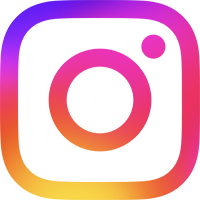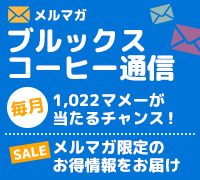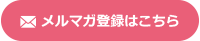- BROOK’S OFFICIAL BLOGトップ >
- ご当地
- > 野菜の文明開化?横浜から広まった西洋野菜たち
野菜の文明開化?横浜から広まった西洋野菜たち

 横浜と聞くと観光やデートスポット、歴史ある港町などさまざまなイメージを連想されるかと思いますが、思いもしない別の一面もあるのです。
横浜と聞くと観光やデートスポット、歴史ある港町などさまざまなイメージを連想されるかと思いますが、思いもしない別の一面もあるのです。
■観光スポット横浜のもうひとつの顔とは?
それは・・・意外にも農業!
映画やドラマのロケ地としても有名な横浜ですが、ほんの少し内陸よりの区では、小松菜生産量が全国トップクラスです。その他にもほうれん草や、みず菜など合計30品目の野菜・果物が市の生産振興品目(横浜ブランド農産物)として認定されるなど、じつは農業が盛んということはあまり知られていません。
そして、その農業についても意外な歴史を持っています。
■文明開化とともにやってきた生で食べられる野菜
開港間もない1863年(文久3年)、横浜居留地に住む英国人ウィリアム・カーティスは山手方面の肥沃な土地に着目。大規模な農園を作って、居留地に住む外国人向けに、キャベツやカリフラワー、トマトなどを栽培していたそうです。  当時の日本でなじみのある野菜と言えば、大根やごぼう、なすに里芋など火を通した煮物や漬物のための根菜が中心でした。
当時の日本でなじみのある野菜と言えば、大根やごぼう、なすに里芋など火を通した煮物や漬物のための根菜が中心でした。
それが開港後、西洋野菜を生で食べるサラダという食べ方が持ち込まれたのをきっかけに、その需要の高まりを受け神奈川奉行が試作栽培を開始。そこから横浜各地へと広がり定着していったのです。
■西洋野菜の料理とコーヒーで気分はハイカラさん
横浜で初めて作られた西洋野菜の品目はトマト・レタス・人参・イチゴなど全部で14種。2009年には開港150周年を記念して、「横濱開港菜」として横浜市から正式に認定されています。中でも横浜らしい「開港菜」の代表格とも言えるのがトマト。
開港以前から日本にトマトはありましたが、それは観賞用だったというから驚きですね。明治に入ってから西洋文化の広がりとともに食用へと変わり、今では毎日のように食卓にあがるほど、すっかり私たちの生活に定着しています。
トマトといえば、調味料として加工されたトマトケチャップも人気です。もともとはアメリカから伝わったとされていますが、国内での製造・販売は横浜から始まったという説が有力視されています。トマトケチャップを使ったナポリタンをはじめ、横浜が発祥の地とされ「横濱開港菜」が、洋食の普及に一役買ったのかもしれませんね。  開港を機に日本に伝わり、少しずつ広がっていった西洋文化。その普及とともに、日本人が洋食やコーヒーを口にする機会も増えてゆきました。
開港を機に日本に伝わり、少しずつ広がっていった西洋文化。その普及とともに、日本人が洋食やコーヒーを口にする機会も増えてゆきました。
遡ること158年前の安政6年6に開港した横浜。そこで6月は「横濱開港菜」を使った料理と、おいしいコーヒーを楽しんでみてはいかがでしょうか。現代では一般的な組み合わせですが、もしかしたら丁髷(ちょんまげ)を結い、刀を差した人たちが同じものを楽しんでいたかも…と想像すると、歴史の浪漫を感じませんか?